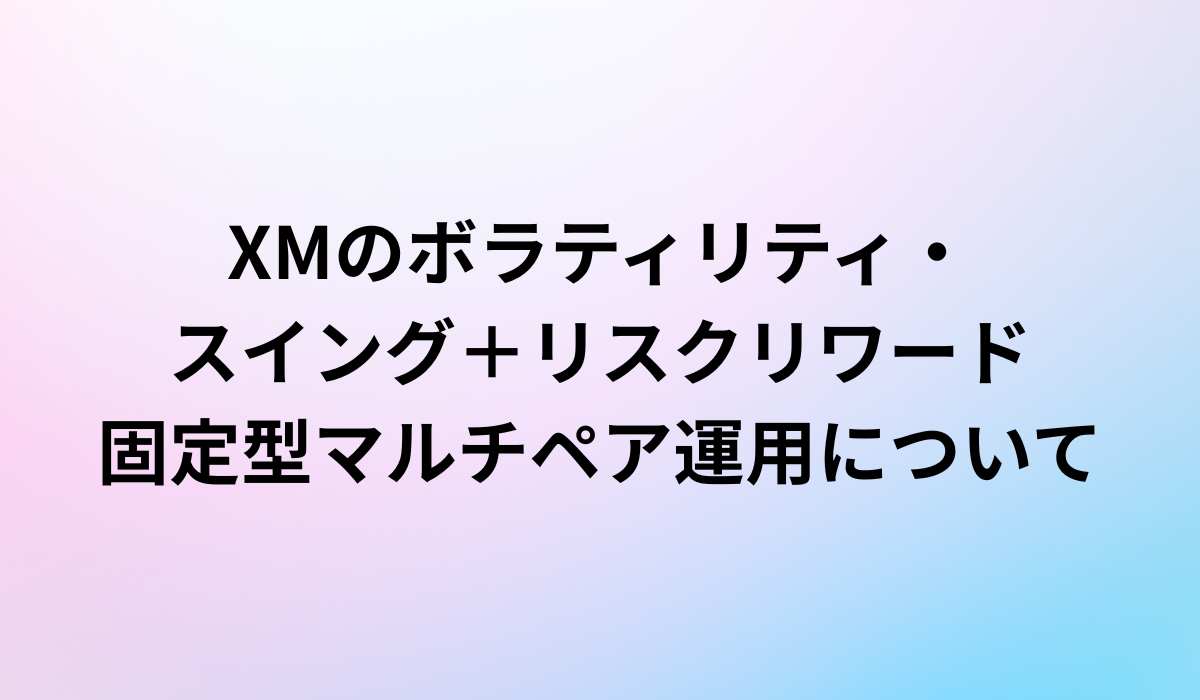「ボラティリティ・スイング+リスクリワード固定型マルチペア運用」は、裁量トレーダー・システムトレーダーの両方にとって非常に洗練された中〜長期のトレンドフォロー戦略です。
この手法は、
📈 各通貨ペア(または銘柄)のボラティリティ特性を活かしながら、
⚖️ 一定のリスクリワード比率を維持し、複数ペアで分散運用することで、
リスク調整後の収益(シャープレシオ)を最大化することを目的としています。
目次
🔶 1. 戦略の全体像
▶ 戦略の基本思想
「一つのペアに依存せず、複数ペアで一定のリスクリワードを保ちながら運用する」ことが主眼です。
各通貨ペアはボラティリティ(価格変動幅)が異なるため、
- 高ボラペア(例:GBPJPY, XAUUSD)は利幅も損幅も大きい
- 低ボラペア(例:EURUSD, USDCHF)は安定だが伸びが小さい
この性質を「ATR(平均的な変動幅)」などのボラティリティ指標で補正し、
すべてのペアで「同じリスク量」に調整して運用します。
🔶 2. ボラティリティ・スイング戦略の基礎
● ボラティリティ・スイングとは?
ボラティリティの拡大・縮小のサイクルを利用して、価格のスイング(波)を狙う戦略です。
典型的な手法:
- ATRや標準偏差を用いて「低ボラ期→高ボラ期」への転換を検出
- ブレイクアウトや押し目・戻り目でエントリー
- トレンド拡大時にリスクリワードを固定して利確・損切
🔶 3. リスクリワード固定型とは?
● 固定型リスクリワードの意図
トレードごとに「勝率」と「損益比率(RR)」を安定化させ、
統計的優位性(エッジ)を明確化するための設計です。
例えば:
- リスクリワード比率:1 : 2(1Rの損失に対して2Rの利益)
- つまり、50pipsの損切なら100pipsで利確。
これにより:
- 勝率40〜50%でも長期的にプラスを維持可能
- 損益の偏りを排除し、ロジック検証が容易になる
🔶 4. マルチペア運用の仕組み
● 運用対象例
- 通貨:USDJPY, EURUSD, GBPJPY, AUDUSD, XAUUSD
- 条件:相関が低めのペアを選択
→ 同時にポジションを持ってもリスクが偏らないようにする
● リスクの調整
各ペアでのポジションサイズを「ATRを用いて調整」します。
例:
- 各通貨ペアのATR(14日)を算出
- EURUSD:ATR = 60pips
- GBPJPY:ATR = 150pips
- 各トレードのリスクを「口座残高の1%」に固定
- すると、GBPJPYはロットをEURUSDの約1/2に調整すべき、という計算になります。
🔶 5. 運用ルールの設計例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エントリー条件 | ATR拡大+MAクロス or ボリンジャーバンドブレイク |
| 損切設定 | ATR × 1.5(または直近スイング高安) |
| 利確設定 | 損切幅 × 2(リスクリワード2:1固定) |
| 通貨ペア | 5〜8ペア(相関低めの組み合わせ) |
| 1トレードのリスク | 口座残高の1〜2%以内 |
| 最大同時ポジション数 | 3〜5ペア(合計リスク=5〜6%以内) |
| 評価期間 | 月単位または四半期単位の統計で勝率・期待値を算出 |
🔶 6. 実践例(具体的なシミュレーション)
| 通貨ペア | ATR(14) | 損切幅 | 利確幅 | ロット | 勝率 | 期待値(1トレード) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 60 | 0.0060 | 0.0120 | 1.0 | 45% | +0.3R |
| GBPJPY | 150 | 0.0150 | 0.0300 | 0.4 | 47% | +0.34R |
| AUDUSD | 55 | 0.0055 | 0.0110 | 1.1 | 43% | +0.26R |
| XAUUSD | 250 | 2.5 | 5.0 | 0.25 | 48% | +0.36R |
合計期待値 ≒ +0.3R/トレード
1R=口座の1%であれば、約+0.3%の期待値。
1か月20トレードで約+6%の理論的成長が見込めます。
🔶 7. この戦略の強みと弱み
✅ 強み
- ボラティリティを基準にした公正なリスク管理
- 相関分散により安定した損益曲線
- 固定RRによりバックテストやEA化が容易
- ボラ拡大期で爆発的に伸びる
⚠️ 弱み
- レンジ相場では「ストップ先行」しやすい(勝率低下)
- 同時に複数ペアでドローダウンを受ける可能性
- 通貨相関(例:USD主導トレンド)で「同方向に動く」場合あり
🔶 8. 改良アイデア
- ボラティリティ・フィルター
ATRが一定水準を超えたペアのみエントリーする
→ トレンド相場のみ狙う - 動的リスクリワード比率
ボラティリティ急拡大時はRRを1:3、
停滞時は1:1.5に自動調整 - 週次ボラティリティ分散運用
週初に全ペアのATR・相関を算出し、
最も「独立した」3ペアを選択運用する
🔶 9. まとめ
| 要素 | 目的 |
|---|---|
| ボラティリティ調整 | 各ペアのリスクを均一化 |
| リスクリワード固定 | 統計的な一貫性を確保 |
| マルチペア分散 | トレンド偏りを軽減 |
| 結果 | 安定したリスク調整後リターン(シャープレシオ↑) |